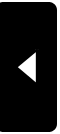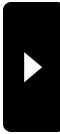2013年07月26日
お出かけ前の車チェック(夏編)
この夏、車での旅行を計画している方も多いのではないでしょうか?
旅先での車のトラブル発生のリスクを少しでも減らすために、こんな準備をしておきましょう。
≪オーバーヒートを防ぐ≫
・ボンネットを開け、LLC(冷却水)とエンジンオイルの液量が適量ライン内にあるか確認
・エンジンオイルは前回の交換から5000kmまたは半年以上経っていたら迷わず交換
≪バッテリー上がりを防ぐ≫
・ボンネットを開け、バッテリーの液量が適量ライン内にあるか確認
・前回の交換から2年以上経っているなら、交換を検討
≪パンクを防ぐ≫
・空気圧が減るとパンクしやすいので、適正値まで空気を補充
≪ガス欠を防ぐ≫
・エアコンを使う夏場は意外とガソリンの減りが早いもの。
お出かけ前は充分な量の給油を!その後も早め早めの給油を心がける
ちょっと面倒ですが、炎天下でエアコンも止まり救助車を待つ・・・
なんてことにならないためにも、お出かけ前のチェック、してみて下さいね。
旅先での車のトラブル発生のリスクを少しでも減らすために、こんな準備をしておきましょう。
≪オーバーヒートを防ぐ≫
・ボンネットを開け、LLC(冷却水)とエンジンオイルの液量が適量ライン内にあるか確認
・エンジンオイルは前回の交換から5000kmまたは半年以上経っていたら迷わず交換
≪バッテリー上がりを防ぐ≫
・ボンネットを開け、バッテリーの液量が適量ライン内にあるか確認
・前回の交換から2年以上経っているなら、交換を検討
≪パンクを防ぐ≫
・空気圧が減るとパンクしやすいので、適正値まで空気を補充
≪ガス欠を防ぐ≫
・エアコンを使う夏場は意外とガソリンの減りが早いもの。
お出かけ前は充分な量の給油を!その後も早め早めの給油を心がける
ちょっと面倒ですが、炎天下でエアコンも止まり救助車を待つ・・・
なんてことにならないためにも、お出かけ前のチェック、してみて下さいね。
2013年07月10日
ドライブシャフトブーツに注目~!
車に起きた不具合は、早期発見でメンテナンス費用を抑えることが出来るものが
多いものです。今回ご紹介する「ドライブシャフトブーツ」もその一つ、早期発見の
コツと、早期交換の必要性についてのお話です。
◎エンジンの力でタイヤを回すドライブシャフト
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ドライブシャフトは、エンジンの駆動をタイヤに伝えるための部品
・タイヤから車体の中心あるデフに向かって、水平に渡された棒状のもの
・シャフトの両端にあるジョイントでデフとタイヤの速度を合わせ、
スムーズに回転させる役割を果たす
・このジョイント部分をほこりや汚れから守るためのカバーがドライブシャフトブーツ
・防水のゴム製で、中にはグリスが充填されている
◎ドライブシャフトブーツは消耗品
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ゴム製のパーツはそもそも消耗品、ブーツもゴム製品
・更に走行で発生する汚れから、ジョイント部分を身を呈して守っている
・汚れによる経年劣化で、いつかは必ず材質が劣化、ヒビ割れてくる
◎ドライブシャフトブーツが破れるとこんなことに・・・
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ブーツにヒビが入ったまま乗り続けると、その部分が切れ、
ジョイント部がむき出しに
・ブーツ内のグリスは飛び散り、ジョイントの内部に水が浸水
・ジョイント部に、サビやほこりによるガタが発生
・ジョイント部の不具合が、次々に関連パーツの不具合や破損を引き起こす
・走行不能で事故につながる場合もあり、命の危険も!!
◎ヒビが無いか、自分で点検しよう
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ハンドルを大きく切って、車から下りる
・タイヤの内側に、円錐形で蛇腹状をしたドライブシャフトブーツが見える
・ブーツを手で触って、破れが無いか確認する
・手にグリスが付く場合は、内部からの漏れ=ひびが疑われるので要注意!
◎こんな車のドライブシャフトブーツは要注意
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・寒冷地・・・気温が低いとゴムは硬くなり、破損しやすくなる
・オフロード走行・・・跳ね石でブーツが傷つきやすい
・古い車・・・長く使用していれば、ゴム製品は当然経年劣化している
発見が遅れてドライブシャフト全体の交換となった場合には、早期発見でブーツ
のみを交換するのと比べると、何倍も費用がかかることもあります。ブーツが
破れていると車検にも通らない事からもわかるように、不具合を放置してよい部分
ではありません。何より安全走行への不安が少しでもあってはなりません。
気をつけなければ気付かない部品ですが、どうぞあなたの定期点検項目の一つに
組み込んで、注意してあげて下さい。
2013年07月01日
◇◇ 県外ナンバー車の車検 ◇◇
住まいは神奈川県にあるけど、仕事の都合で半年だけ車と一緒に静岡県に単身赴任。
その間に車検があるけどどうすればいい?
こういうケース、仕事でなくても意外とあるものです。
近くならまだしも、車検のためだけに2時間も運転して神奈川県に戻る、
というのも面倒ですよね。
こんな時はご心配なく!
車検に必要な書類(車検証・納税証明書・自賠責保険証)が揃っていれば、
県外ナンバーでも問題なく、今いる県で車検を受けることができるんです。
書類が不足している場合でも、車検証と自賠責保険証はすぐに再発行が出来ますが、
納税証明書は他県からの取り寄せに時間がかかる場合があります。
その間に車検期限が・・・ということがないように、ゆとりを持ってお近くの店舗に
車検をご予約下さい!
その間に車検があるけどどうすればいい?
こういうケース、仕事でなくても意外とあるものです。
近くならまだしも、車検のためだけに2時間も運転して神奈川県に戻る、
というのも面倒ですよね。
こんな時はご心配なく!
車検に必要な書類(車検証・納税証明書・自賠責保険証)が揃っていれば、
県外ナンバーでも問題なく、今いる県で車検を受けることができるんです。
書類が不足している場合でも、車検証と自賠責保険証はすぐに再発行が出来ますが、
納税証明書は他県からの取り寄せに時間がかかる場合があります。
その間に車検期限が・・・ということがないように、ゆとりを持ってお近くの店舗に
車検をご予約下さい!
2013年06月04日
自動車税を払わないとこんなことに!
毎年5月末は自動車税の納付期限、もう皆さん納付済ですよね。
この自動車税、支払わないとどんなことになるかご存知でしょうか?
まず、督促状が届きます。ここで払っておけば問題ないのですが、さらに支払いを
怠ると延滞金も掛ってきます。
それでも払わないと・・・車や家財や財産、口座などの差し押さえが執行されるんです。
口座からの強制的な引き落としで済めばいいんですが、それで足りないと
差し押さえられた車などは競売に掛けられて売られてしまう、なんていう事態に。
「そこまでは・・・」という方も、納税証明書がないと車検に通りませんので、
車検までには支払いを済ませておいて下さい。
いえ、そもそも督促状がくる時点で税金の無駄遣いをしているようなもの。
「あっ忘れてた!」という方は早々に自動車税納付を済ませて下さいね!!
この自動車税、支払わないとどんなことになるかご存知でしょうか?
まず、督促状が届きます。ここで払っておけば問題ないのですが、さらに支払いを
怠ると延滞金も掛ってきます。

それでも払わないと・・・車や家財や財産、口座などの差し押さえが執行されるんです。
口座からの強制的な引き落としで済めばいいんですが、それで足りないと
差し押さえられた車などは競売に掛けられて売られてしまう、なんていう事態に。
「そこまでは・・・」という方も、納税証明書がないと車検に通りませんので、
車検までには支払いを済ませておいて下さい。
いえ、そもそも督促状がくる時点で税金の無駄遣いをしているようなもの。
「あっ忘れてた!」という方は早々に自動車税納付を済ませて下さいね!!
2013年05月31日
エンジンオイルキャンペーン 開催のお知らせ
エンジンオイルキャンペーン 開催
6月1日・3日・4日・5日 受付時間 9:00~17:00
この期間中 エンジンオイル 1ℓ 100円 で交換できます。
しかもオイルの質も純正オイルと一緒のグレード!!
こんなチャンスなかなかない。
その他多種オイルご用意あります。
ご希望の方はお申し出ください。
この機会ぜひお見逃しなく!!
6月1日・3日・4日・5日 受付時間 9:00~17:00
この期間中 エンジンオイル 1ℓ 100円 で交換できます。
しかもオイルの質も純正オイルと一緒のグレード!!
こんなチャンスなかなかない。
その他多種オイルご用意あります。
ご希望の方はお申し出ください。
この機会ぜひお見逃しなく!!
2013年05月18日
2013年05月01日
オーバーヒート時のウソ?ホント?
エンジンの冷却が上手くいかなくて、エンジンを冷やす冷却水の温度が上がり
過ぎてしまうオーバーヒート。このオーバーヒートの対処法として、「エンジンは
切らないこと」と言われていますが、これってホント?
昔の車はそうでしたが、最近の車は必ずしもそうではありません。
水温が上がってしまうというのは、冷却系統のトラブルが原因。
冷却水が漏れて少なくなっている時にエンジンを回し続けると、エンジンに余計に
ダメージを与えてしまうことに。まずはエンジンを止めてエンジンを冷ましてから、
ラジエーターの状態を確認してください。
熱いうちにラジエーターキャップを外したりすると、熱湯が噴き出して危険なので
くれぐれもご注意を!!
過ぎてしまうオーバーヒート。このオーバーヒートの対処法として、「エンジンは
切らないこと」と言われていますが、これってホント?
昔の車はそうでしたが、最近の車は必ずしもそうではありません。
水温が上がってしまうというのは、冷却系統のトラブルが原因。

冷却水が漏れて少なくなっている時にエンジンを回し続けると、エンジンに余計に
ダメージを与えてしまうことに。まずはエンジンを止めてエンジンを冷ましてから、
ラジエーターの状態を確認してください。
熱いうちにラジエーターキャップを外したりすると、熱湯が噴き出して危険なので
くれぐれもご注意を!!

2013年04月03日
命を守る、ブレーキ回りのメンテ
車の基本性能「走る・曲がる・止まる」はどれも大切な要素ですが、中でも「止まる」は
運転者や歩行者の命を守る上でとても大切なものです。
今回は、その「止まる」を支えるブレーキ回りのメンテナンスについてお話しします。
◎まずはブレーキの種類から
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ブレーキには、走行中に使うフットブレーキと、停止中に使うパーキングブレーキがある
・フットブレーキは、大きく分けると2種類
・一つはディスクブレーキ、車輪と一緒に回転するディスクを両側からパッドで挟んで
回転を止め、ブレーキをかける
・もう一つはドラムブレーキ、車輪と一緒に回転するドラムの内側にブレーキライニングを
押しつけて回転を止め、ブレーキをかける
・どちらのブレーキも一長一短の特性があるが、大型トラックなどはドラムブレーキが多い
・乗用車の場合は、前輪はディスクブレーキ、後輪はドラムブレーキが一般的
◎ブレーキパッドは残厚をチェック
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ブレーキパッドは消耗品、ディスクとの摩擦によって厚みが減ってきたら交換する
・減り方はパッドの素材や車種、運転者のクセなどでも違ってくる
・大体3~4万キロ、早ければ2万キロで交換が必要になることも
・コバックでは、4mm以下なら交換をお勧めしている
・車検や12ヶ月点検の時には必ず残厚の確認をしている
・自分で確認する時は、タイヤを外すと現れるブレーキキャリパーについている点検孔
から見ることができる
・足回りから「キーキー」と音が出始めたら、パッドの残量が減った知らせ
・そのまま乗り続けると、ブレーキディスクごと交換が必要になってしまい、交換費用も
高くなるので要注意!
◎ブレーキローターも消耗品
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ブレーキをかける時にブレーキパッドが押しつけられる部分がブレーキローター
・摩擦によってレコード盤のように筋状の削れ痕ができる
・点検時には異常なキズのつき方をしていないか確認する
・ブレーキローターも消耗品、摩擦熱やこすれによる摩耗が進むと、
ひび割れやひずみができてブレーキの性能を落とす
・ローターの表面を研磨して再利用することもできるが、薄くなるため強度が
不安、新品への交換がお勧め
◎ブレーキライニングも残量をチェック
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ドラムブレーキの場合、ブレーキパットと同じ役目をするのがブレーキライニング
・コバックでは、残量2mm以下なら交換をお勧めしている
・点検方法や注意事項はブレーキパッドと同じ
◎劣化しやすいブレーキオイルも交換必須
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・油圧で作動するブレーキ、この油圧の「油」がブレーキオイル
・ブレーキオイルの入ったタンクは、車体手前から見てエンジンルームの奥の方にある
・日常点検では、適量か?色の汚れが無いか?を確認する
・量は多くても少なくてもダメ、MAXとMINの目盛りの間にあること
・量が減るようなら漏れの疑い、液を補充する前に原因を調べ修理すること
・ブレーキオイルは湿気を吸収しやすく、これが劣化の原因になる
・ブレーキオイルは鮮度が大切!車検ごとの定期交換がお勧め
・劣化すると、ブレーキの効きが悪くなってキケン!
・更にはブレーキシリンダーが腐食して、それごと交換が必要になる
・交換の際はエア抜き作業が必要
いずれも自分でやってできない事はないけど、ちょっと高いレベルのメンテナンス。
重要保安部品でもあり、万一のリスクも考えるとプロに任せた方が安心でしょう。
車検のコバック各店でも承っていますので、お気軽にご相談下さい!
運転者や歩行者の命を守る上でとても大切なものです。
今回は、その「止まる」を支えるブレーキ回りのメンテナンスについてお話しします。
◎まずはブレーキの種類から
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ブレーキには、走行中に使うフットブレーキと、停止中に使うパーキングブレーキがある
・フットブレーキは、大きく分けると2種類
・一つはディスクブレーキ、車輪と一緒に回転するディスクを両側からパッドで挟んで
回転を止め、ブレーキをかける
・もう一つはドラムブレーキ、車輪と一緒に回転するドラムの内側にブレーキライニングを
押しつけて回転を止め、ブレーキをかける
・どちらのブレーキも一長一短の特性があるが、大型トラックなどはドラムブレーキが多い
・乗用車の場合は、前輪はディスクブレーキ、後輪はドラムブレーキが一般的
◎ブレーキパッドは残厚をチェック
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ブレーキパッドは消耗品、ディスクとの摩擦によって厚みが減ってきたら交換する
・減り方はパッドの素材や車種、運転者のクセなどでも違ってくる
・大体3~4万キロ、早ければ2万キロで交換が必要になることも
・コバックでは、4mm以下なら交換をお勧めしている
・車検や12ヶ月点検の時には必ず残厚の確認をしている
・自分で確認する時は、タイヤを外すと現れるブレーキキャリパーについている点検孔
から見ることができる
・足回りから「キーキー」と音が出始めたら、パッドの残量が減った知らせ
・そのまま乗り続けると、ブレーキディスクごと交換が必要になってしまい、交換費用も
高くなるので要注意!
◎ブレーキローターも消耗品
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ブレーキをかける時にブレーキパッドが押しつけられる部分がブレーキローター
・摩擦によってレコード盤のように筋状の削れ痕ができる
・点検時には異常なキズのつき方をしていないか確認する
・ブレーキローターも消耗品、摩擦熱やこすれによる摩耗が進むと、
ひび割れやひずみができてブレーキの性能を落とす
・ローターの表面を研磨して再利用することもできるが、薄くなるため強度が
不安、新品への交換がお勧め
◎ブレーキライニングも残量をチェック
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ドラムブレーキの場合、ブレーキパットと同じ役目をするのがブレーキライニング
・コバックでは、残量2mm以下なら交換をお勧めしている
・点検方法や注意事項はブレーキパッドと同じ
◎劣化しやすいブレーキオイルも交換必須
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・油圧で作動するブレーキ、この油圧の「油」がブレーキオイル
・ブレーキオイルの入ったタンクは、車体手前から見てエンジンルームの奥の方にある
・日常点検では、適量か?色の汚れが無いか?を確認する
・量は多くても少なくてもダメ、MAXとMINの目盛りの間にあること
・量が減るようなら漏れの疑い、液を補充する前に原因を調べ修理すること
・ブレーキオイルは湿気を吸収しやすく、これが劣化の原因になる
・ブレーキオイルは鮮度が大切!車検ごとの定期交換がお勧め
・劣化すると、ブレーキの効きが悪くなってキケン!
・更にはブレーキシリンダーが腐食して、それごと交換が必要になる
・交換の際はエア抜き作業が必要
いずれも自分でやってできない事はないけど、ちょっと高いレベルのメンテナンス。
重要保安部品でもあり、万一のリスクも考えるとプロに任せた方が安心でしょう。
車検のコバック各店でも承っていますので、お気軽にご相談下さい!
2013年03月30日
自賠責料金が値上げ
平成25年4月1日分から自賠責保険料が改定(引き上げ)になりました。
これは、平成20年に自賠責保険料の累積残高の還元を目的に大幅な
値下げが実施された際、それを平成25年までに元の保険料水準に戻すことが既に予定されており、
これに従って平成23年と平成25年の2段階に分けて引き上げられるものです。
≪改定後の自賠責料金≫
乗用車 現行:24,950円 → 改定後:27,840円(+2,890円)
軽自動車 現行:21,970円 → 改定後:26,370円(+4,400円)
※全車種平均で13.5%の引き上げです(引き下げになる車種もあります)
お手元の車検の見積書とは金額が異なる場合がありますので、車検の際はご注意ください。
ちなみに自賠責保険料は全国どこで車検を受けても同じ金額です(離島を除く)。
国で決まったこととは言え、何かと物入りなこの季節にキビシー値上げになりますね。
これは、平成20年に自賠責保険料の累積残高の還元を目的に大幅な
値下げが実施された際、それを平成25年までに元の保険料水準に戻すことが既に予定されており、
これに従って平成23年と平成25年の2段階に分けて引き上げられるものです。
≪改定後の自賠責料金≫
乗用車 現行:24,950円 → 改定後:27,840円(+2,890円)
軽自動車 現行:21,970円 → 改定後:26,370円(+4,400円)
※全車種平均で13.5%の引き上げです(引き下げになる車種もあります)
お手元の車検の見積書とは金額が異なる場合がありますので、車検の際はご注意ください。
ちなみに自賠責保険料は全国どこで車検を受けても同じ金額です(離島を除く)。
国で決まったこととは言え、何かと物入りなこの季節にキビシー値上げになりますね。
2013年02月22日
車検とは?
車に乗っていると、2年に1回必ず受けなければいけない車検。
「決められているからやっているだけ」という方も多いのではないでしょうか?
今回は身近にあるけどなんだかわかりにくい、車検のことをわかりやすくご紹介します。
◎そもそも「車検」とは?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・人の命を乗せて走る車、これを定期的に検査するのが車検
・道路運送車輌法の保安基準に適合しているかどうかを確認する
・目的は「走行の安全を確保すること」と
「部品劣化により発生する公害を未然に防ぐこと」
・機械である車は、部品の消耗や劣化によって必ず不具合が発生するもの
・「車が故障したことないから車検なんて必要ない!」と言うあなた、
車検があったからこそ故障が無かったのです
◎車検を受けないとどうなる?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車検切れの車を公道で運転すると道路交通法の処罰対象となる
・その罰の重さは単なる整備不良と大違い、免停90日と罰金が科せられる
・もし免停の前歴があれば一発で免許取り消し!日常生活への大打撃は間違いない
・公道を走れないとなると、車検のために店舗に車を持ち込むのも一苦労
・市役所で仮ナンバーを申請して入手するか、積載車で車を運ばなければならない
◎車検の中身を知っていますか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車検整備の中身はこの3つ
1) 法廷24ヶ月定期点検・・・約60項目の重要保安箇所の点検
2) 完成検査・・・ブレーキやヘッドライト、排気ガス等の検査
3) 更新手続き・・・陸運支局での車検証とステッカーの更新手続き
・数万点の部品で構成されている車を2年に1回点検する車検
・それぞれの部品が法律の基準を満たす状態でなければ車検に合格できない
・不具合が見つかった場合、そのための整備費用は別途必要になる
◎車検費用の内訳を知っていますか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車検費用は主にこの4つ
1) 車検料・・・点検・検査及び更新手続きの費用
2) 自賠責保険料・・・必ず加入しなければならない強制保険の保険料
3) 重量税・・・車検及び新車購入の時に支払う税金
4) 印紙代・・・更新手続きの際、国に手数料を納めるための印紙
・この内、店舗が手にするのは1)車検料のみ
・2)3)4)は全て国に納める性質のもの、店舗は一旦お金を預かるに過ぎない
・2)3)4)は基本的にどこで車検を受けても同額、安い車検を探すなら1)に注目しよう
◎すぐに車検がわかるQ&A
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車検はいつから受けられる?
→1ヶ月前からなら、早く受けても車検期限は短くならない
・他人名義の車でも車検を受けられる?
→受けられるが、15日以内に変更手続きをすることが法律で決められている
ので速やかに手続きを!
・引越し前の住所のままでも車検を受けられる?
→受けられるが、こちらも名義変更と同じく15日以内に変更手続きが必要
・他県ナンバーでも車検を受けられる?
→大丈夫。ただ、納税証明書が無くて取り寄せる場合は時間がかかるので、
その間に車検切れにならないよう要注意
・自動車税を納めてなくても車検を受けられる?
→NO、事前に納めた事を示す納税証明書が必ず必要
・前回の車検で入った自賠責保険証を無くしちゃった!
→大丈夫。ただし、通常より1ヶ月余分に契約することが必要
◎車検証のこんな記載をご存知ですか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車検証の裏側にはこんな記載がある
「自動車所有者へのお知らせ・・・自動車の検査は、安全・環境の面について国が
定める基準に適合しているかどうかを一定期間ごとに確認するものであり、次の
検査までの安全性等を保証するものではありません。したがって、使用者は、
日常点検整備や定期点検整備を確実に実施するとともに、使用状況に応じて
適切に保守管理を行う必要があります」
・車検はその時点での適合状況を見るもの、その後は車の所有者の責任において
車を管理しなければならない
・車検を受けたら次の車検までノーメンテ、なんていうのはご法度なので気を付けて!
「車検後すぐに不具合が発生した!」というトラブルが発生することがあります。
車検時に交換したり取り外したりした部品の場合、それが原因であることもあるのですが、
車検時には大丈夫だったけど車検後すぐのタイミングでその部品の寿命が来てしまった、
というケースがほとんど。消耗部品の集合体である車の宿命ともいえるでしょう。
不具合で車が使えないとなると、車のありがたさが身に染みます。
車への感謝の気持ちを忘れず、愛情を持って継続的なメンテナンスをしてあげて下さいね。
「決められているからやっているだけ」という方も多いのではないでしょうか?
今回は身近にあるけどなんだかわかりにくい、車検のことをわかりやすくご紹介します。
◎そもそも「車検」とは?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・人の命を乗せて走る車、これを定期的に検査するのが車検
・道路運送車輌法の保安基準に適合しているかどうかを確認する
・目的は「走行の安全を確保すること」と
「部品劣化により発生する公害を未然に防ぐこと」
・機械である車は、部品の消耗や劣化によって必ず不具合が発生するもの
・「車が故障したことないから車検なんて必要ない!」と言うあなた、
車検があったからこそ故障が無かったのです
◎車検を受けないとどうなる?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車検切れの車を公道で運転すると道路交通法の処罰対象となる
・その罰の重さは単なる整備不良と大違い、免停90日と罰金が科せられる
・もし免停の前歴があれば一発で免許取り消し!日常生活への大打撃は間違いない
・公道を走れないとなると、車検のために店舗に車を持ち込むのも一苦労
・市役所で仮ナンバーを申請して入手するか、積載車で車を運ばなければならない
◎車検の中身を知っていますか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車検整備の中身はこの3つ
1) 法廷24ヶ月定期点検・・・約60項目の重要保安箇所の点検
2) 完成検査・・・ブレーキやヘッドライト、排気ガス等の検査
3) 更新手続き・・・陸運支局での車検証とステッカーの更新手続き
・数万点の部品で構成されている車を2年に1回点検する車検
・それぞれの部品が法律の基準を満たす状態でなければ車検に合格できない
・不具合が見つかった場合、そのための整備費用は別途必要になる
◎車検費用の内訳を知っていますか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車検費用は主にこの4つ
1) 車検料・・・点検・検査及び更新手続きの費用
2) 自賠責保険料・・・必ず加入しなければならない強制保険の保険料
3) 重量税・・・車検及び新車購入の時に支払う税金
4) 印紙代・・・更新手続きの際、国に手数料を納めるための印紙
・この内、店舗が手にするのは1)車検料のみ
・2)3)4)は全て国に納める性質のもの、店舗は一旦お金を預かるに過ぎない
・2)3)4)は基本的にどこで車検を受けても同額、安い車検を探すなら1)に注目しよう
◎すぐに車検がわかるQ&A
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車検はいつから受けられる?
→1ヶ月前からなら、早く受けても車検期限は短くならない
・他人名義の車でも車検を受けられる?
→受けられるが、15日以内に変更手続きをすることが法律で決められている
ので速やかに手続きを!
・引越し前の住所のままでも車検を受けられる?
→受けられるが、こちらも名義変更と同じく15日以内に変更手続きが必要
・他県ナンバーでも車検を受けられる?
→大丈夫。ただ、納税証明書が無くて取り寄せる場合は時間がかかるので、
その間に車検切れにならないよう要注意
・自動車税を納めてなくても車検を受けられる?
→NO、事前に納めた事を示す納税証明書が必ず必要
・前回の車検で入った自賠責保険証を無くしちゃった!
→大丈夫。ただし、通常より1ヶ月余分に契約することが必要
◎車検証のこんな記載をご存知ですか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車検証の裏側にはこんな記載がある
「自動車所有者へのお知らせ・・・自動車の検査は、安全・環境の面について国が
定める基準に適合しているかどうかを一定期間ごとに確認するものであり、次の
検査までの安全性等を保証するものではありません。したがって、使用者は、
日常点検整備や定期点検整備を確実に実施するとともに、使用状況に応じて
適切に保守管理を行う必要があります」
・車検はその時点での適合状況を見るもの、その後は車の所有者の責任において
車を管理しなければならない
・車検を受けたら次の車検までノーメンテ、なんていうのはご法度なので気を付けて!
「車検後すぐに不具合が発生した!」というトラブルが発生することがあります。
車検時に交換したり取り外したりした部品の場合、それが原因であることもあるのですが、
車検時には大丈夫だったけど車検後すぐのタイミングでその部品の寿命が来てしまった、
というケースがほとんど。消耗部品の集合体である車の宿命ともいえるでしょう。
不具合で車が使えないとなると、車のありがたさが身に染みます。
車への感謝の気持ちを忘れず、愛情を持って継続的なメンテナンスをしてあげて下さいね。
2013年01月29日
オイル交換基礎知識
エンジンオイルは車のエンジンをスムーズに動かすために無くてはならない存在。
最も身近な車のメンテナンスであるエンジンオイル交換ですが、勧められるままに
交換するだけで、自分ではよくわかっていないという方もいるのではないでしょうか?
今回は超初心者向け、オイル交換の基礎知識をお届けします。
◎オイル交換の重要性を知るべし!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・エンジンが充分に性能を発揮するために、欠かせないのがエンジンオイル
・オイルは消耗品。量も減るし、劣化もする
・オイルが古くなったり、少なくなったまま使っていると、エンジン故障の原因に
・エンジンの故障=とんでもない高額な出費の可能性(><)
・走行中にエンジン不調で停止=事故の可能性、キケン(><)
・こうしたトラブルを未然に防ぐためにもオイル交換は欠かせない
◎オイル交換は定期的に行うべし!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・エンジンオイルの交換目安は5000キロまたは6ヶ月ごと
・「6000キロまで交換せずに乗れた!」と欲張っても、いい事は何にも無い
・オイル交換の時期は、自分での管理が必要
・年間走行距離が1万キロ未満なら、1月と6月といったように決めてしまうとよい
・一方を車検の月に合わせれば、2年に1度はわざわざオイル交換に行く手間が省ける
・自分で決めて、オイル交換をサイクルに組み込もう
◎車に合ったオイルを選ぶべし!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・お店にずら~っと並ぶエンジンオイル、値段はピンからキリまで、どれを選ぶ?
・高い方がエンジンに良さそう・・・おっと、それは大間違い!
・値段ではなく、自分の車に合ったオイルを選ぶことが大切
・車の取扱説明書を見ると、最適なオイルの記載がある
・不安なら、資格と知識を持った整備士のいる整備工場に相談すれば安心
◎オイルは適量を守るべし!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・自分でオイル交換、「どうせ減るから多めに入れとこう」なんてことは?
・オイルは、少なくても多過ぎてもエンジン不調の原因となる
・オイルゲージのLとFの間の量を守ること
・自分で交換しない場合も、月に1度はオイルの量を確認するとよい
・ボンネットを開けて、オイルゲージを一旦拭き取ってから、再度差し込んで量を見る
・この時、平らな場所に駐車し、エンジンを止めて5分程度待ってから確認すること
◎オイルフィルターも定期的に交換すべし!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・オイルの汚れや異物をろ過するフィルター、オイルエレメントとも呼ばれる
・フィルターがひどく汚れていると、せっかく交換したオイルの汚れの原因に
・フィルターが詰まれば、スムーズなオイルの循環もできない
・オイル交換の2回に1回は、オイルフィルターも交換すること
自分でオイル交換のサイクルを管理していれば、オイルやフィルターの交換を
勧められても、「次は○月に交換するので結構です」と自信を持って断りやすい
ですよね。メカに疎い、といった方でも比較的理解しやすいオイル交換、まずは
ここから、自分の車のメンテナンス管理を始めてみませんか?
最も身近な車のメンテナンスであるエンジンオイル交換ですが、勧められるままに
交換するだけで、自分ではよくわかっていないという方もいるのではないでしょうか?
今回は超初心者向け、オイル交換の基礎知識をお届けします。
◎オイル交換の重要性を知るべし!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・エンジンが充分に性能を発揮するために、欠かせないのがエンジンオイル
・オイルは消耗品。量も減るし、劣化もする
・オイルが古くなったり、少なくなったまま使っていると、エンジン故障の原因に
・エンジンの故障=とんでもない高額な出費の可能性(><)
・走行中にエンジン不調で停止=事故の可能性、キケン(><)
・こうしたトラブルを未然に防ぐためにもオイル交換は欠かせない
◎オイル交換は定期的に行うべし!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・エンジンオイルの交換目安は5000キロまたは6ヶ月ごと
・「6000キロまで交換せずに乗れた!」と欲張っても、いい事は何にも無い
・オイル交換の時期は、自分での管理が必要
・年間走行距離が1万キロ未満なら、1月と6月といったように決めてしまうとよい
・一方を車検の月に合わせれば、2年に1度はわざわざオイル交換に行く手間が省ける
・自分で決めて、オイル交換をサイクルに組み込もう
◎車に合ったオイルを選ぶべし!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・お店にずら~っと並ぶエンジンオイル、値段はピンからキリまで、どれを選ぶ?
・高い方がエンジンに良さそう・・・おっと、それは大間違い!
・値段ではなく、自分の車に合ったオイルを選ぶことが大切
・車の取扱説明書を見ると、最適なオイルの記載がある
・不安なら、資格と知識を持った整備士のいる整備工場に相談すれば安心
◎オイルは適量を守るべし!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・自分でオイル交換、「どうせ減るから多めに入れとこう」なんてことは?
・オイルは、少なくても多過ぎてもエンジン不調の原因となる
・オイルゲージのLとFの間の量を守ること
・自分で交換しない場合も、月に1度はオイルの量を確認するとよい
・ボンネットを開けて、オイルゲージを一旦拭き取ってから、再度差し込んで量を見る
・この時、平らな場所に駐車し、エンジンを止めて5分程度待ってから確認すること
◎オイルフィルターも定期的に交換すべし!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・オイルの汚れや異物をろ過するフィルター、オイルエレメントとも呼ばれる
・フィルターがひどく汚れていると、せっかく交換したオイルの汚れの原因に
・フィルターが詰まれば、スムーズなオイルの循環もできない
・オイル交換の2回に1回は、オイルフィルターも交換すること
自分でオイル交換のサイクルを管理していれば、オイルやフィルターの交換を
勧められても、「次は○月に交換するので結構です」と自信を持って断りやすい
ですよね。メカに疎い、といった方でも比較的理解しやすいオイル交換、まずは
ここから、自分の車のメンテナンス管理を始めてみませんか?
2013年01月25日
自賠責保険料の値上げ決定!
1月17日に実施された政府の自賠責保険審議会で、平成25年4月1日からの
車検時に諸費用として、支払われる自賠責保険料改定(引き上げ)が決定しました。
これは自賠責保険料の累積残高 の還元を目的に平成20年に大幅な値下げが実施された際、
それを平成25年までに元の保険料水準に戻すことが既に予定されており、
これに従って平成23年と平成25年の2段階に分けて引き上げられたものです。
≪改定後の24ヶ月自賠責料金≫
乗用車 現行:24,950円 → 改定後:27,840円(+2,890円)
軽自動車 現行:21,970円 → 改定後:26,370円(+4,400円)
※全車種平均で13.5%の引き上げです(引き下げになる車種もあります)
元の水準に・・・とは言え、家計には痛~い値上げとなりそうですね。
車検時に諸費用として、支払われる自賠責保険料改定(引き上げ)が決定しました。
これは自賠責保険料の累積残高 の還元を目的に平成20年に大幅な値下げが実施された際、
それを平成25年までに元の保険料水準に戻すことが既に予定されており、
これに従って平成23年と平成25年の2段階に分けて引き上げられたものです。
≪改定後の24ヶ月自賠責料金≫
乗用車 現行:24,950円 → 改定後:27,840円(+2,890円)
軽自動車 現行:21,970円 → 改定後:26,370円(+4,400円)
※全車種平均で13.5%の引き上げです(引き下げになる車種もあります)
元の水準に・・・とは言え、家計には痛~い値上げとなりそうですね。
2012年12月26日
車の寿命は10年10万キロなの?
昔は車の寿命は「10年10万キロ」なんて言われていましたが、現在の車は高性能
で長持ち。「車検ごとに車を乗り換える!」なんて人もずいぶん減って、1台の車に
永~く乗る人も増えてきました。
今回は10万キロを超えた車のメンテナンスについてのお話です。
◎10万キロ突破、おめでとうございます!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・いよいよ走行距離10万キロ突破!さて、何をする?
・答えは・・・すぐにしなければならない事は何もない
・それまで定期点検のたびに必要なメンテナンスをしていたなら、これまで通り
それを続けるだけ
・点検で見つかった不具合を整備するとともに、オイルなどの消耗品を早めに交換する
◎車は10万キロを超えると壊れやすい?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・定期的な整備をしてさえいれば、今どきの車は10万キロくらいへっちゃら
・エンジンオイル、ブレーキオイルなどの油脂類に加え、ベルト類やブレーキパッド
などのゴム製品、スパークプラグなどの消耗品を、交換基準に添って怠りなく交換
していれば、快適な走行が続けられる
・それでもやはり年が経てば、トラブルが起こるリスクは高くなる
・それを未然に防ぐためのメンテナンスを見てみよう
◎タイミングベルトはそろそろ替え時!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・エンジンを動かす重要部品、これが切れると車は動かない
・ベルトはゴム製品なので経年による品質劣化は避けられない
・10万キロを超えたらいつ切れてもおかしくない、交換しておく方が安心
・最近はベルトの替わりにチェーンを使っている車が多い
・チェーンはあまり交換例はないが、それまでのメンテナンス不足によって
異音がすることも
・その場合はチェーンであっても交換が必要な場合がある
◎こんなところも気を付けて!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ウォーターポンプ(エンジンのオーバーヒートを防ぐためのLLCが入っている)
・ハブベアリング(タイヤをスムーズに回転させるための部品)
・オートマオイル(オートマチック・トランスミッションをスムーズに動かすためのオイル)
・不具合があれば迷わず交換することで、そこから派生する高額な故障を防げる
◎予防整備がカーライフコスト削減のカギ!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車は多くの部品が機能して動いている
・これらの部品がいつまで快適に動くかは、やはりメンテナンス次第
・メンテナンスはお金がかかるから、調子が悪くなったら車を買い替えれはいい?
・いえいえ、車種や乗り方、予防整備状態にもよるが、車を買い替えるよりは
予防整備のが絶対にお得!
・車検・点検時のアドバイスには充分耳を傾け、予防整備でカーライフコストを
削減しながら、快適なカーライフを送ろう!
「10万キロを超えた」といっても、実はその10万キロに至るまでのメンテナンスこそが重要。
10万キロを超えたからといって、それから整備を始めても、ちょっと手遅れの感は否めません。
車を手に入れたその日から、10年後の愛車を見据えてのお手入れが必要なんですね。
で長持ち。「車検ごとに車を乗り換える!」なんて人もずいぶん減って、1台の車に
永~く乗る人も増えてきました。
今回は10万キロを超えた車のメンテナンスについてのお話です。
◎10万キロ突破、おめでとうございます!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・いよいよ走行距離10万キロ突破!さて、何をする?
・答えは・・・すぐにしなければならない事は何もない
・それまで定期点検のたびに必要なメンテナンスをしていたなら、これまで通り
それを続けるだけ
・点検で見つかった不具合を整備するとともに、オイルなどの消耗品を早めに交換する
◎車は10万キロを超えると壊れやすい?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・定期的な整備をしてさえいれば、今どきの車は10万キロくらいへっちゃら
・エンジンオイル、ブレーキオイルなどの油脂類に加え、ベルト類やブレーキパッド
などのゴム製品、スパークプラグなどの消耗品を、交換基準に添って怠りなく交換
していれば、快適な走行が続けられる
・それでもやはり年が経てば、トラブルが起こるリスクは高くなる
・それを未然に防ぐためのメンテナンスを見てみよう
◎タイミングベルトはそろそろ替え時!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・エンジンを動かす重要部品、これが切れると車は動かない
・ベルトはゴム製品なので経年による品質劣化は避けられない
・10万キロを超えたらいつ切れてもおかしくない、交換しておく方が安心
・最近はベルトの替わりにチェーンを使っている車が多い
・チェーンはあまり交換例はないが、それまでのメンテナンス不足によって
異音がすることも
・その場合はチェーンであっても交換が必要な場合がある
◎こんなところも気を付けて!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ウォーターポンプ(エンジンのオーバーヒートを防ぐためのLLCが入っている)
・ハブベアリング(タイヤをスムーズに回転させるための部品)
・オートマオイル(オートマチック・トランスミッションをスムーズに動かすためのオイル)
・不具合があれば迷わず交換することで、そこから派生する高額な故障を防げる
◎予防整備がカーライフコスト削減のカギ!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車は多くの部品が機能して動いている
・これらの部品がいつまで快適に動くかは、やはりメンテナンス次第
・メンテナンスはお金がかかるから、調子が悪くなったら車を買い替えれはいい?
・いえいえ、車種や乗り方、予防整備状態にもよるが、車を買い替えるよりは
予防整備のが絶対にお得!
・車検・点検時のアドバイスには充分耳を傾け、予防整備でカーライフコストを
削減しながら、快適なカーライフを送ろう!
「10万キロを超えた」といっても、実はその10万キロに至るまでのメンテナンスこそが重要。
10万キロを超えたからといって、それから整備を始めても、ちょっと手遅れの感は否めません。
車を手に入れたその日から、10年後の愛車を見据えてのお手入れが必要なんですね。
2012年12月25日
年末年始の休業日のお知らせ
皆さんお正月休みはどうのようにお過ごしされる予定でしょうか?
もう車のメンテナンスはお済ですか?
まだお済みでない方は是非一度点検に来て下さいね。
年末年始の休業日のお知らせ
2012年12月30日(土) ~ 2013年1月4日(金)
ご不便おかけしますが、よろしくお願い致します。
もう車のメンテナンスはお済ですか?
まだお済みでない方は是非一度点検に来て下さいね。
年末年始の休業日のお知らせ
2012年12月30日(土) ~ 2013年1月4日(金)
ご不便おかけしますが、よろしくお願い致します。
2012年12月01日
雪道走行の心得
いよいよ冬本番、慣れない雪道走行、怖いですよね。
思いがけない突然の降雪で、走らざるを得なくなることも。
いざという時に備えて、雪道走行の心得を知っておきましょう。
◎「雪道」といっても色々
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・一言で雪道といっても色々、状況によって危険度は変わる
・圧雪・・・雪が踏み固められた状態、凍結よりは安全だが油断禁物
・アイスバーン・・・一旦溶けた雪が夜凍って氷のようになった状態、超危険
・新雪・・・一面真っ白で道路の境目が分からない
溝にハマったり、吹き溜まりに突っ込んだりしやすいので路肩に注意
・シャーベット状・・・比較的危険は少ないが、歩行者に泥はねしないように気を付けて
◎雪道走行ではここに注意!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・雪道は予想以上に路面が滑ることを念頭に置いて、安全速度で走行する
・急発進、急ハンドル、急ブレーキはもちろん厳禁、車間距離も多めに
・下り坂は、フットブレーキとエンジンブレーキも使って速度をコントロール
・発進時と上り坂は、じんわりとアクセルを踏みこむように
≪ガス欠≫
・極寒の中でのガス欠、想像してみてください(寒っっ)
・動かなくなった車は渋滞の原因、周りの車にも大迷惑
≪タイヤ≫
・積雪や凍結で滑る恐れのある道路をノーマルタイヤで走ることは道交法違反、
罰則の対象になる
・最近のスタッドレスタイヤは高性能、でも過信は禁物、絶対に滑らないタイヤなんてない
≪チェーン≫
・必ずタイヤサイズに合ったものを用意して、事前に一度装着してみること
・スピードの出し過ぎや緩みはチェーン切れの原因、異音がしたら必ず降りて確認して!
≪吹雪・地吹雪≫
・吹雪いて前が真っ白で見えない!そんな時はゆっくり速度を落として、
ハザードランプも忘れずに
・吹雪の中での走行は、ハイビームよりもロービームで、少し先の路面に目を凝らす
・フォグランプは対向車からの視認に有効、あればすぐに点灯を
≪凍結抑制剤≫
・滑りやすい場所に散布するだけで、道路全部をカバーしている訳ではない
・散布後も降雪が続くと、効果が低減してしまうので要注意!
≪4WD≫
・4輪駆動車だから滑らない!というのは大間違い、一度滑りだしたら立て直しは困難
・FF(前輪駆動車)でもFR(後輪駆動車)でもそれぞれの特性の危険がある
◎お出かけの前に準備、準備!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・行き先はもちろん、道中の気象条件・道路状況もチェックして
・冬装備は早め早めに!
・備え必須の雪道グッズ
軍手・スコップ・タイヤチェーン・けん引ロープ・ブースターケーブル
防寒着・長靴・懐中電灯 など
・その他、ワイパーや冷却水(LLC)を雪国仕様に変えておくと安心
・雪道ではウィンドウォッシャー液は必需品、液量チェックも怠りなく
◎こんな場所は特にキケン、と知っておこう!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・雪道では危険な場所や状況を早め早めに予測しながらの運転が必要
・長い下り坂・・・緩やかな坂道でも一旦スリップし始めると停まれない!!
・峠・・・急カーブや日陰は凍結が残っている場所が多い
・トンネル・・・山から風が吹き下ろして、出入口付近だけ凍結している場合がある
・橋・・・吹きっさらしなのでとっても凍りやすい!
・早朝・・・前日の凍結の上に積雪があると、とっても滑りやすい
・除雪作業車・・・追い抜く時、除雪前後の段差でハンドルを取られやすい
・雪の回廊・・・吹き溜まりができやすい、乗り上げると脱出が困難
◎スタッドレスタイヤは寿命に注意!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・まだ溝があるから安心?いいえ、スタッドレスはゴムが劣化して
グリップ力が落ちたら寿命
・いくら性能のいいタイヤでも、劣化しないゴムは無い
・硬度計でゴムがまだ固くなっていないかを確認!
最近の車はABS(アンチロック・ブレーキ・システム)がついていますが、
これはあくまで安全をサポートするためのもの。
雪道走行の安全性は運転者の安全運転と正しい判断にかかっています。
備え万全、安全運転で、冬のドライブを楽しんでくださいね。
思いがけない突然の降雪で、走らざるを得なくなることも。
いざという時に備えて、雪道走行の心得を知っておきましょう。
◎「雪道」といっても色々
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・一言で雪道といっても色々、状況によって危険度は変わる
・圧雪・・・雪が踏み固められた状態、凍結よりは安全だが油断禁物
・アイスバーン・・・一旦溶けた雪が夜凍って氷のようになった状態、超危険
・新雪・・・一面真っ白で道路の境目が分からない
溝にハマったり、吹き溜まりに突っ込んだりしやすいので路肩に注意
・シャーベット状・・・比較的危険は少ないが、歩行者に泥はねしないように気を付けて
◎雪道走行ではここに注意!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・雪道は予想以上に路面が滑ることを念頭に置いて、安全速度で走行する
・急発進、急ハンドル、急ブレーキはもちろん厳禁、車間距離も多めに
・下り坂は、フットブレーキとエンジンブレーキも使って速度をコントロール
・発進時と上り坂は、じんわりとアクセルを踏みこむように
≪ガス欠≫
・極寒の中でのガス欠、想像してみてください(寒っっ)
・動かなくなった車は渋滞の原因、周りの車にも大迷惑
≪タイヤ≫
・積雪や凍結で滑る恐れのある道路をノーマルタイヤで走ることは道交法違反、
罰則の対象になる
・最近のスタッドレスタイヤは高性能、でも過信は禁物、絶対に滑らないタイヤなんてない
≪チェーン≫
・必ずタイヤサイズに合ったものを用意して、事前に一度装着してみること
・スピードの出し過ぎや緩みはチェーン切れの原因、異音がしたら必ず降りて確認して!
≪吹雪・地吹雪≫
・吹雪いて前が真っ白で見えない!そんな時はゆっくり速度を落として、
ハザードランプも忘れずに
・吹雪の中での走行は、ハイビームよりもロービームで、少し先の路面に目を凝らす
・フォグランプは対向車からの視認に有効、あればすぐに点灯を
≪凍結抑制剤≫
・滑りやすい場所に散布するだけで、道路全部をカバーしている訳ではない
・散布後も降雪が続くと、効果が低減してしまうので要注意!
≪4WD≫
・4輪駆動車だから滑らない!というのは大間違い、一度滑りだしたら立て直しは困難
・FF(前輪駆動車)でもFR(後輪駆動車)でもそれぞれの特性の危険がある
◎お出かけの前に準備、準備!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・行き先はもちろん、道中の気象条件・道路状況もチェックして
・冬装備は早め早めに!
・備え必須の雪道グッズ
軍手・スコップ・タイヤチェーン・けん引ロープ・ブースターケーブル
防寒着・長靴・懐中電灯 など
・その他、ワイパーや冷却水(LLC)を雪国仕様に変えておくと安心
・雪道ではウィンドウォッシャー液は必需品、液量チェックも怠りなく
◎こんな場所は特にキケン、と知っておこう!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・雪道では危険な場所や状況を早め早めに予測しながらの運転が必要
・長い下り坂・・・緩やかな坂道でも一旦スリップし始めると停まれない!!
・峠・・・急カーブや日陰は凍結が残っている場所が多い
・トンネル・・・山から風が吹き下ろして、出入口付近だけ凍結している場合がある
・橋・・・吹きっさらしなのでとっても凍りやすい!
・早朝・・・前日の凍結の上に積雪があると、とっても滑りやすい
・除雪作業車・・・追い抜く時、除雪前後の段差でハンドルを取られやすい
・雪の回廊・・・吹き溜まりができやすい、乗り上げると脱出が困難
◎スタッドレスタイヤは寿命に注意!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・まだ溝があるから安心?いいえ、スタッドレスはゴムが劣化して
グリップ力が落ちたら寿命
・いくら性能のいいタイヤでも、劣化しないゴムは無い
・硬度計でゴムがまだ固くなっていないかを確認!
最近の車はABS(アンチロック・ブレーキ・システム)がついていますが、
これはあくまで安全をサポートするためのもの。
雪道走行の安全性は運転者の安全運転と正しい判断にかかっています。
備え万全、安全運転で、冬のドライブを楽しんでくださいね。
2012年10月27日
「あっ、パンク!!」そんな時・・・
ドライブ中に「あっ、パンク!!」
自分でタイヤ交換をしたことが無い、と言う方も多いのではないでしょうか?
今回は、いざというときのために、安全なタイヤ交換方法を復習しましょう。
◎タイヤ交換はドライバーの必須テク!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車に乗っている以上、いつ必要になるかわからないのがタイヤ交換
・パンクによるスペアタイヤへの交換や、急な積雪でスタッドレスタイヤへの交換、
自分でできるのに越したことは無い
・知識では知っていても意外としたことのないタイヤ交換方法を復習しよう!
◎まずは車から工具を取り出そう!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車には、ジャッキとホイールレンチ、スペアタイヤが積んである
・いざという時あわてない為に、自分の車で置き場所を確認しておこう
・セダンなら、トランクの底のボードをはがすと見つかる事が多い
・見つからなければ車の取扱説明書を見て探そう
・ジャッキは車に固定してあるので、ハンドルをかける所を回して緩めてから取り外すこと
・逆にしまう時は、ある程度締めて固定して収納すること
・標準では搭載されていないが安全確保の為に輪止めがあるとベスト、ぜひ用意して
◎ジャッキアップ前に安全確保
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ジャッキアップした車は不安定、必ず平らで安定した場所で作業すること
・人が乗ったままよりも、降りて安全な場所で待っていてもらう方が安心
・基本的にはエンジンも停止して、サイドブレーキを引き、シフトをPレンジ
(マニュアル車ならバックギア)にしておく
・前輪を交換する時は後輪に、後輪交換の時は前輪に輪止めをして固定する
◎いよいよジャッキアップ!慎重に
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・まずはアップする前にタイヤのホイールナット(ホイールを固定するねじ)を、
ホイールレンチ(L字型のスティックみたいなの)を使って少し緩める
・固くて緩まない場合は、ナットレンチの柄が真横より上になるようにナットにはめて、
柄を両足で踏んで緩めると良い
・ジャッキはジャッキポイントにセットすること
・ドアよりも更に下の部分、両サイドの前輪と後輪の間に、前後2ヶ所ずつ用意されている
・横からのぞいて切り欠きが2個あったらその間に、1個の場合はその場所にジャッキを置く
・ポイントを間違えると、ボディがゆがんだり、重大な事故につながったりするので注意!
・慎重にジャッキの受け皿の溝とジャッキポイントの場所を合わせたら、
ジャッキの先端の穴にジャッキのハンドルを通してくるくる回しながらジャッキを上げていく
・途中、傾きや揺れなどの異常が無いか気を配ること
・タイヤが5センチほど地面から浮いたらストップ、ナットを緩めてタイヤを外す
・外したタイヤは、万一ジャッキが外れても車体が破損しないように、車の下に寝かせておくこと
◎スペアタイヤをはめる
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・スペアタイヤのホイールの穴とボルトの位置を合わせてはめる
・ホイールナットをまずは手で回し、次にホイールレンチで軽く締めて仮止めする
・ネジを締める時は対角上に順番に締める
・車の下に置いたタイヤをどけて、ジャッキを回しながら静かに車を下におろす
・ジャッキが外れる所まで下ろしたら、ホイールレンチでナットを締めつける
・両手でギューっと締めれば大丈夫、緩める時みたいに全体重をかけてしまうと
締め過ぎでネジ山を傷めることがあるので要注意
◎あると便利!タイヤ交換が楽になるグッズ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・油圧ジャッキ・・・軽くレバーを上下するだけでジャッキアップできるすぐれもの
・クロスレンチ・・・十字型のレンチで、これがあるとホイールナットの脱着が楽チン
・軍手・・・タイヤ交換で手が汚れたり、冬の作業では防寒にと必須!
自分でできればもちろんいいけど、タイヤ交換は中々の重労働。
タイヤは命を預かる重要な部分でもあるので、いざという時以外はプロに任せる、
というのも選択肢の一つですよね。
自分でタイヤ交換をしたことが無い、と言う方も多いのではないでしょうか?
今回は、いざというときのために、安全なタイヤ交換方法を復習しましょう。
◎タイヤ交換はドライバーの必須テク!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車に乗っている以上、いつ必要になるかわからないのがタイヤ交換
・パンクによるスペアタイヤへの交換や、急な積雪でスタッドレスタイヤへの交換、
自分でできるのに越したことは無い
・知識では知っていても意外としたことのないタイヤ交換方法を復習しよう!
◎まずは車から工具を取り出そう!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車には、ジャッキとホイールレンチ、スペアタイヤが積んである
・いざという時あわてない為に、自分の車で置き場所を確認しておこう
・セダンなら、トランクの底のボードをはがすと見つかる事が多い
・見つからなければ車の取扱説明書を見て探そう
・ジャッキは車に固定してあるので、ハンドルをかける所を回して緩めてから取り外すこと
・逆にしまう時は、ある程度締めて固定して収納すること
・標準では搭載されていないが安全確保の為に輪止めがあるとベスト、ぜひ用意して
◎ジャッキアップ前に安全確保
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ジャッキアップした車は不安定、必ず平らで安定した場所で作業すること
・人が乗ったままよりも、降りて安全な場所で待っていてもらう方が安心
・基本的にはエンジンも停止して、サイドブレーキを引き、シフトをPレンジ
(マニュアル車ならバックギア)にしておく
・前輪を交換する時は後輪に、後輪交換の時は前輪に輪止めをして固定する
◎いよいよジャッキアップ!慎重に
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・まずはアップする前にタイヤのホイールナット(ホイールを固定するねじ)を、
ホイールレンチ(L字型のスティックみたいなの)を使って少し緩める
・固くて緩まない場合は、ナットレンチの柄が真横より上になるようにナットにはめて、
柄を両足で踏んで緩めると良い
・ジャッキはジャッキポイントにセットすること
・ドアよりも更に下の部分、両サイドの前輪と後輪の間に、前後2ヶ所ずつ用意されている
・横からのぞいて切り欠きが2個あったらその間に、1個の場合はその場所にジャッキを置く
・ポイントを間違えると、ボディがゆがんだり、重大な事故につながったりするので注意!
・慎重にジャッキの受け皿の溝とジャッキポイントの場所を合わせたら、
ジャッキの先端の穴にジャッキのハンドルを通してくるくる回しながらジャッキを上げていく
・途中、傾きや揺れなどの異常が無いか気を配ること
・タイヤが5センチほど地面から浮いたらストップ、ナットを緩めてタイヤを外す
・外したタイヤは、万一ジャッキが外れても車体が破損しないように、車の下に寝かせておくこと
◎スペアタイヤをはめる
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・スペアタイヤのホイールの穴とボルトの位置を合わせてはめる
・ホイールナットをまずは手で回し、次にホイールレンチで軽く締めて仮止めする
・ネジを締める時は対角上に順番に締める
・車の下に置いたタイヤをどけて、ジャッキを回しながら静かに車を下におろす
・ジャッキが外れる所まで下ろしたら、ホイールレンチでナットを締めつける
・両手でギューっと締めれば大丈夫、緩める時みたいに全体重をかけてしまうと
締め過ぎでネジ山を傷めることがあるので要注意
◎あると便利!タイヤ交換が楽になるグッズ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・油圧ジャッキ・・・軽くレバーを上下するだけでジャッキアップできるすぐれもの
・クロスレンチ・・・十字型のレンチで、これがあるとホイールナットの脱着が楽チン
・軍手・・・タイヤ交換で手が汚れたり、冬の作業では防寒にと必須!
自分でできればもちろんいいけど、タイヤ交換は中々の重労働。
タイヤは命を預かる重要な部分でもあるので、いざという時以外はプロに任せる、
というのも選択肢の一つですよね。
2012年09月18日
スパークプラグでエンジン快調!
車が快調に走行するための3要素は「良い火花」「良い圧縮」「良い混合比」と
言われます。このどれが欠けても不調が起きる訳ですが、今回はその中の一つ
「良い火花」を作るスパークプラグについてのお話です。
◎小さいけど重要なスパークプラグ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・スパークプラグ(プラグ)は、直径1~2センチ×長さ5~7センチくらいの小さな棒状の部品
・エンジンに取り付けるネジの長さ・太さに合わせて、非常に多くの種類がある
・直接熱を受ける部品のため劣化しやすい
・劣化したまま使い続けると、エンジンの不調の原因になる
◎プラグの理想は「こんがりきつね色」
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・エンジンを適切に点火するには適切な温度が必要
・プラグの先端を見て、「きつね色」に焦げ色がついていれば一番いい具合
・黒かったり、白すぎたり、ぼろぼろになっていたりするのは温度が適切でない証拠
・現在の車は電子制御されているのであまり心配はないが、それでも時々プラグを
点検しておくと安心
◎プラグは消耗品
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・これまでの話でもわかるように、プラグは消耗品
・耐久性が高い製品でも、必ず摩耗して、電極の先端が丸くなっていく
・摩耗が進むと思うように火花を飛ばすことができないので、正常な燃焼ができず、
燃費の低下につながる
・プラグの劣化はプラグを外してみないとわからない
・燃費が悪くなった、と感じたら、一度プラグを点検してみよう
◎どのプラグがおすすめ?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・プラグは使用されている金属によって、値段と耐久性が大きく違う
・イリジウムプラグ・・・耐久性が非常に高いイリジウム合金を使用しているので、
高価だが永持ち
・白金プラグ・・・イリジウムほどではないが高性能で永持ち、やっぱり高価
・レジスタープラグ・・・一般的なプラグで、性能や耐久性はやや落ちるが非常に安価
・プラグはエンジンの形状に合わせて様々な種類があるので、それを変えないこと
・一つのエンジンには、全部同じ種類のプラグを使うこと
・プラグは摩耗状態を目で見て判断して交換する部品
・白金プラグの普及で、10万キロが寿命と言われるようになったプラグだが、
実際は7~8キロで摩耗が限界になるケースもあるので油断禁物!
プラグは徐々に摩耗するため、「調子が悪い」と言うのは気付きにくいのですが、
交換をすると「調子が良くなった!」というのは体感できます。
時々は点検して、いつも気持ちよく乗りたいものですね。
自分ではちょっと・・・と言う方は、車検や整備の際にお気軽に点検を依頼して下さい。
言われます。このどれが欠けても不調が起きる訳ですが、今回はその中の一つ
「良い火花」を作るスパークプラグについてのお話です。
◎小さいけど重要なスパークプラグ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・スパークプラグ(プラグ)は、直径1~2センチ×長さ5~7センチくらいの小さな棒状の部品
・エンジンに取り付けるネジの長さ・太さに合わせて、非常に多くの種類がある
・直接熱を受ける部品のため劣化しやすい
・劣化したまま使い続けると、エンジンの不調の原因になる
◎プラグの理想は「こんがりきつね色」
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・エンジンを適切に点火するには適切な温度が必要
・プラグの先端を見て、「きつね色」に焦げ色がついていれば一番いい具合
・黒かったり、白すぎたり、ぼろぼろになっていたりするのは温度が適切でない証拠
・現在の車は電子制御されているのであまり心配はないが、それでも時々プラグを
点検しておくと安心
◎プラグは消耗品
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・これまでの話でもわかるように、プラグは消耗品
・耐久性が高い製品でも、必ず摩耗して、電極の先端が丸くなっていく
・摩耗が進むと思うように火花を飛ばすことができないので、正常な燃焼ができず、
燃費の低下につながる
・プラグの劣化はプラグを外してみないとわからない
・燃費が悪くなった、と感じたら、一度プラグを点検してみよう
◎どのプラグがおすすめ?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・プラグは使用されている金属によって、値段と耐久性が大きく違う
・イリジウムプラグ・・・耐久性が非常に高いイリジウム合金を使用しているので、
高価だが永持ち
・白金プラグ・・・イリジウムほどではないが高性能で永持ち、やっぱり高価
・レジスタープラグ・・・一般的なプラグで、性能や耐久性はやや落ちるが非常に安価
・プラグはエンジンの形状に合わせて様々な種類があるので、それを変えないこと
・一つのエンジンには、全部同じ種類のプラグを使うこと
・プラグは摩耗状態を目で見て判断して交換する部品
・白金プラグの普及で、10万キロが寿命と言われるようになったプラグだが、
実際は7~8キロで摩耗が限界になるケースもあるので油断禁物!
プラグは徐々に摩耗するため、「調子が悪い」と言うのは気付きにくいのですが、
交換をすると「調子が良くなった!」というのは体感できます。
時々は点検して、いつも気持ちよく乗りたいものですね。
自分ではちょっと・・・と言う方は、車検や整備の際にお気軽に点検を依頼して下さい。
2012年09月01日
バッテリー上がりの対処法
バッテリー上がりの対処法
バッテリーが上がってしまった時のお助けツールといえば「ブースターケーブル」。
いざという時には本当に助かるのですが、使い方を間違えるとキケンなことも。
今回は正しい使い方を復習してみましょう。
≪用意するもの≫
・ブースターケーブル
・助けてくれる車(以下、正常車)
・そして、バッテリーがあがった車(以下、故障車)
≪手順≫
1. 2台の車をバッテリー同士が近づくように停める
2.正常車のエンジンを始動したまま、次の順番でブースターケーブルのクリップで挟む
1)赤いケーブルを故障車のバッテリーの+端子へ
2)赤いケーブルを正常車のバッテリーの+端子へ
3)黒いケーブルを正常車のバッテリーの-端子へ
4)黒いケーブルを故障車のエンジンの金属部分へ
(エンジンを吊下げるフックなど、どこでもよい)
3.1分ほど待ってから故障車のエンジンを始動する
4.両方の車のエンジンをかけたまま挟んだのと逆の手順で(4→1)ブースターケーブルを外す
故障車は一度エンジンを停めてしまうとまたかからなくなってしまう可能性が大なので、
そのまま整備工場やカー用品店に向かって、バッテリーの点検を受けて下さい。
ブースターケーブルはホームセンターなどで売っています。
車に1つ常備しておくと安心ですよ。
あっ、それから乗用車とトラックは電圧が違う場合が多いので、
必ず同じ電圧の車同士をつないで下さいね。
※車によっては上記手順と異なる場合がありますので、車の取扱説明書で確認してください。
※上記手順でかからない場合、自分では難しい場合はロードサービスを呼んで下さい。
バッテリーが上がってしまった時のお助けツールといえば「ブースターケーブル」。
いざという時には本当に助かるのですが、使い方を間違えるとキケンなことも。
今回は正しい使い方を復習してみましょう。
≪用意するもの≫
・ブースターケーブル
・助けてくれる車(以下、正常車)
・そして、バッテリーがあがった車(以下、故障車)
≪手順≫
1. 2台の車をバッテリー同士が近づくように停める
2.正常車のエンジンを始動したまま、次の順番でブースターケーブルのクリップで挟む
1)赤いケーブルを故障車のバッテリーの+端子へ
2)赤いケーブルを正常車のバッテリーの+端子へ
3)黒いケーブルを正常車のバッテリーの-端子へ
4)黒いケーブルを故障車のエンジンの金属部分へ
(エンジンを吊下げるフックなど、どこでもよい)
3.1分ほど待ってから故障車のエンジンを始動する
4.両方の車のエンジンをかけたまま挟んだのと逆の手順で(4→1)ブースターケーブルを外す
故障車は一度エンジンを停めてしまうとまたかからなくなってしまう可能性が大なので、
そのまま整備工場やカー用品店に向かって、バッテリーの点検を受けて下さい。
ブースターケーブルはホームセンターなどで売っています。
車に1つ常備しておくと安心ですよ。
あっ、それから乗用車とトラックは電圧が違う場合が多いので、
必ず同じ電圧の車同士をつないで下さいね。
※車によっては上記手順と異なる場合がありますので、車の取扱説明書で確認してください。
※上記手順でかからない場合、自分では難しい場合はロードサービスを呼んで下さい。
2012年08月10日
夏季休暇のお知らせ
夏休み前の車のメンテナンスは済んでますか
連休を使って遠出する方は点検を済ませておいて下さい
夏季休暇のお知らせ
8月11日~8月16日
ご不便おかけしますが、よろしくお願い致します。

連休を使って遠出する方は点検を済ませておいて下さい

夏季休暇のお知らせ
8月11日~8月16日
ご不便おかけしますが、よろしくお願い致します。
2012年08月01日
日常点検、してますか?
車の日常点検、「自動車学校では習ったけど、やったことはない」という方が
多いのでは?でもこれは道路運送車両法で自動車の使用者に定められた義務、
必ずやらなければならない事なんです。
今回は、日常点検のやり方をおさらいしてみましょう。
◎毎朝するのはめんどくさい!?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・法令では、「使用者が判断した適切な時期に実施」とある
・普通の自家用車の場合は、使用状況に応じて行なえばいい
・業務用など法令で指定された一部の車両は、毎日1回運行前の実施が必要
・忘れないように、○日とか、給油の時になど、自分で点検する日を決めておくといい
◎日常点検のチェックポイント≪車のまわりを回ってチェック≫
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・まず運転席側前方に立ち、時計回りにぐるっと1周
・ヘッドライト・・・汚れや損傷はないか、正常に点灯するか
・ブレーキランプ・・・汚れや損傷はないか、正常に点灯するか
・タイヤ・・・空気圧、溝の深さ、亀裂・破損はないか
・特にタイヤ側面の亀裂や、溝に挟まった小石は、
走行中のパンクやバーストに繋がりやすいので要注意
・ついでにバンパーやボディのキズも確認して、キズにはサビ防止を
◎日常点検のチェックポイント≪エンジンルームをのぞいてチェック≫
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ブレーキフルード・・・液量が上限と下限ラインの間にあるか
・バッテリー・・・液量が規定範囲内にあるか
・エンジンオイル・・・液量がオイルレベルゲージのL-Fの間にあり、汚れが無いか
・ウォッシャー・・・液量が適切か
・LLC(冷却水)・・・液量がタンクの上限ラインまであるか
◎日常点検のチェックポイント≪運転席に座ってチェック≫
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・サイドブレーキ・・・引きしろは多過ぎたり少な過ぎたりしないか
・エンジン・・・速やかにかかり、異音は無いか
・ブレーキペダル・・・踏みしろは適当か
・ウォッシャー液・・・うまく噴射できるか
・ワイパー・・・きれいに拭き取れるか
◎日常点検のチェックポイント≪走行してチェック≫
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ブレーキ・・・効き具合は適切か
・エンジン・・・アイドリング時のエンジン回転は一定で、スムーズな加速ができるか
◎日常点検をすると、いいことたくさん!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車の現状を把握し、まめにチェックする事で、すぐに異常に気づけるようになる
・それにより早期発見、早期メンテナンスができる
・メカトラブルの未然防止、快適走行、車永持ちといいことづくめ
・手順を知って慣れれば簡単、ぜひ習慣にしよう
車のいつもの状態を正しく把握しているからこそ、「何か違う?」にいち早く
気付いてあげる事ができるんですね。特に長距離走行前には日時点検を
しておくと安心ですので、お盆休みに帰省や旅行などで車を使う場合は、
ぜひ実施してみて下さい。
多いのでは?でもこれは道路運送車両法で自動車の使用者に定められた義務、
必ずやらなければならない事なんです。
今回は、日常点検のやり方をおさらいしてみましょう。
◎毎朝するのはめんどくさい!?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・法令では、「使用者が判断した適切な時期に実施」とある
・普通の自家用車の場合は、使用状況に応じて行なえばいい
・業務用など法令で指定された一部の車両は、毎日1回運行前の実施が必要
・忘れないように、○日とか、給油の時になど、自分で点検する日を決めておくといい
◎日常点検のチェックポイント≪車のまわりを回ってチェック≫
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・まず運転席側前方に立ち、時計回りにぐるっと1周
・ヘッドライト・・・汚れや損傷はないか、正常に点灯するか
・ブレーキランプ・・・汚れや損傷はないか、正常に点灯するか
・タイヤ・・・空気圧、溝の深さ、亀裂・破損はないか
・特にタイヤ側面の亀裂や、溝に挟まった小石は、
走行中のパンクやバーストに繋がりやすいので要注意
・ついでにバンパーやボディのキズも確認して、キズにはサビ防止を
◎日常点検のチェックポイント≪エンジンルームをのぞいてチェック≫
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ブレーキフルード・・・液量が上限と下限ラインの間にあるか
・バッテリー・・・液量が規定範囲内にあるか
・エンジンオイル・・・液量がオイルレベルゲージのL-Fの間にあり、汚れが無いか
・ウォッシャー・・・液量が適切か
・LLC(冷却水)・・・液量がタンクの上限ラインまであるか
◎日常点検のチェックポイント≪運転席に座ってチェック≫
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・サイドブレーキ・・・引きしろは多過ぎたり少な過ぎたりしないか
・エンジン・・・速やかにかかり、異音は無いか
・ブレーキペダル・・・踏みしろは適当か
・ウォッシャー液・・・うまく噴射できるか
・ワイパー・・・きれいに拭き取れるか
◎日常点検のチェックポイント≪走行してチェック≫
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ブレーキ・・・効き具合は適切か
・エンジン・・・アイドリング時のエンジン回転は一定で、スムーズな加速ができるか
◎日常点検をすると、いいことたくさん!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・車の現状を把握し、まめにチェックする事で、すぐに異常に気づけるようになる
・それにより早期発見、早期メンテナンスができる
・メカトラブルの未然防止、快適走行、車永持ちといいことづくめ
・手順を知って慣れれば簡単、ぜひ習慣にしよう
車のいつもの状態を正しく把握しているからこそ、「何か違う?」にいち早く
気付いてあげる事ができるんですね。特に長距離走行前には日時点検を
しておくと安心ですので、お盆休みに帰省や旅行などで車を使う場合は、
ぜひ実施してみて下さい。